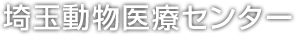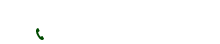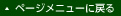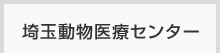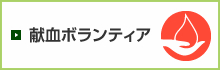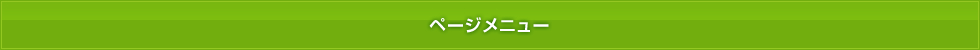ホルモンの病気
副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)
副腎皮質機能亢進症は副腎が腫れて過剰な副腎ホルモンが体の中に放出されるために様々な症状が起きる病気です。
主な症状
- 多飲多尿(お水をたくさん飲んでたくさんのおしっこをする)
- おなかが張ってきたり,たるんできたりする.
- 毛が薄くなる
- 異常な食欲
- 足腰が弱くなる
- 血栓(血のかたまり)が出来ることによる呼吸困難
- 突然死
などがあげられます。
副腎皮質機能亢進症には大きく分けて下垂体性と副腎腫瘍性の2つのタイプがあります。
|
下垂体性 |
脳の下垂体が腫瘍化(多くは良性)して副腎へ過剰な指令を送ってしまいます。 その過剰な指令を副腎が受け取ることで異常な副腎ホルモンが体内に放出されます。 また、このタイプは更に下垂体小型腺腫(約 82 %)と下垂体巨大腺腫( 15 %),癌(約 3 %)の 3 つのタイプがあり、通常、小型腺腫は内科療法に対する反応が良好ですが巨大腺腫は副作用(神経症状)が強く発現し治療に危険性が高くなります。 癌について は非常に少ないため、治療効果などもよくわかっていません。 これらの鑑別は CT スキャン検査が必要です。 |
|---|---|
| 副腎腫瘍性 ( 10 ~ 20 %) |
副腎自体が腫瘍化して異常なホルモンを放出します。 副腎の評価はエコー検査と CT スキャン検査が有効です。 |
治療 下垂体性クッシング症候群
1.内科療法
飲み薬で 副腎から出されるホルモン(コルチゾール)ホルモンの機能を抑制します。
| トリロスタン |
副腎から出てくるホルモンの機能をブロックするお薬です。
比較的新しいお薬で、副腎を破壊しないために、従来のお薬(ミトタンなど)と比べ副作用が少ないのが特徴です。治療効果はミトタンと同等かそれ以上と考えられています。現在はミトタンに変わり、トリロスタンが第一選択薬になっています。
|
|---|---|
| ミトタン | このお薬は副腎を直接破壊することで副腎からのホルモン放出を少なくします。効果は比較的高く、以前はこのお薬が第一選択で使用されていましたが、現在はトリロスタンでの管理が難しい症例に使用することがあります。しかし、欠点として副作用が比較的多く、副腎を壊しすぎてしまうと下痢、嘔吐、食欲不振などの症状が見られ、重症例では副腎皮質機能低下症に陥り逆にホルモンを補充する必要が出てきます。 |
2.外科療法
腫瘍化した下垂体を手術で摘出します。理想的な治療法ですが、まだ世界的にも実績が少なく、確立された治療ではありません。
術後には副腎ホルモンも甲状腺ホルモンも全くでなくなるためホルモン補充療法が一生必要になります。
3. 放射線治療
下垂体腫瘍の中で巨大腺腫と呼ばれる大きな腫瘍の場合に適用になります。
放射線で腫瘍化した下垂体を破壊してしまう方法です。
特殊な施設が必要で,残念ながら現在日本で下垂体に対する放射線治療が行える施設は限られています。
治療 副腎腫瘍性クッシング症候群
1.外科療法
副腎腫瘍の治療の第一選択は外科手術による腫瘍化した副腎の摘出になります。
2.内科療法
お薬(内服薬)で副腎を破壊する治療となりますが下垂体性に比べ効果が少なく、様々な理由で手術が不可能な場合に選択される治療法です。
※進行するとあえぎ呼吸、腹囲膨大・下垂、元気の低下、筋力の低下、神経症状、肺血栓塞栓症などで命にかかわります。
甲状腺機能低下症
甲状腺機能低下症は甲状腺ホルモンが分泌されなくなり様々な症状が出てくる病気で、高齢の犬に発症が多いです。
主な症状
-
毛が薄くなる
-
太りやすくなる
-
元気がなくなる
-
皮膚がベタベタしたり、皮膚炎や外耳炎になりやすくなったりする
-
高脂血症
甲状腺機能低下症には大きく分けて2つのタイプがあります。
|
1次性
甲状腺機能低下症
|
甲状腺自体の異常でホルモンが分泌できなくなる。犬の甲状腺機能低下症ではほとんどがこちらに入ります。 |
|---|---|
| 2次性 甲状腺機能低下症 |
視床下部や下垂体から甲状腺への指令がうまく行えなくなった結果、甲状腺ホルモンの分泌が低下してしまいます。 |
検査・診断
-
甲状腺ホルモン濃度測定(T4、fT4、TSHなど)
多くは上記の検査で診断がつきますが、診断が困難な場合は以下の検査を実施することもあります。 -
血中高サイログロブリン抗体測定
-
甲状腺の超音波検査
-
TSH刺激試験
治療
飲み薬で甲状腺ホルモンを補う治療を行います。
- レボチロキシンナトリウム製剤:製剤によって1日1~2回の投薬が必要になります。
定期的にホルモンの濃度を測定して、お薬の量を調節していきます。
甲状腺機能亢進症
どんな病気?
喉のあたりに存在する甲状腺から分泌されるホルモンが、様々な原因により過剰に分泌されてしまう疾患です。犬・猫ともに起こる疾患ですが、犬では機能低下症の方が多く見られ、機能亢進症は稀な疾患であることから、ここでは猫で多く見られる内分泌疾患としてご紹介します。
症状
中・高齢での発症が多く「よく食べるのに痩せてくる」という症状がよく見られます。甲状腺ホルモンは体の代謝に関わっていることから、他にも嘔吐・下痢・多飲多尿・高血圧・落ち着きがなくなるなど、様々な症状が見られます。
診断
まずは食欲や元気さ、家での様子についての問診を行います。次に体重の変化や聴診・触診をした上で、発症が疑われる場合は血液検査や血圧測定を行います。そして、甲状腺ホルモンの値が基準値を超えていれば機能亢進症と診断します。
治療
飲み薬による内科治療と、大きくなった甲状腺を摘出する外科治療があります。治療開始後は腎臓をはじめとした他臓器の機能とのバランスが重要になる為、定期的な検査が必要になります。
おわりに
「高齢だけど元気でよく食べるし、痩せてるのは歳のせいかな」と様子を見ていると、病気の発見が遅れてしまうことがあります。少しでも気になることがあれば、早めに受診されることをおすすめします。
糖尿病
糖尿病とは、インスリンという膵臓から分泌されるホルモンの作用が十分に働かなくなる病気です。インスリン作用が不足すると、血液中の糖を細胞内に取り込めず、エネルギー源として利用できなくなります。その結果、高血糖が持続し尿糖も出現します。
症状としては、多飲多尿、多食、体重減少、末梢神経症状などが認められます。
インスリン作用が不足する要因としては、大きく2つに分類されます。
1つは、インスリンを分泌する膵臓β細胞が破壊され、インスリンが産生できないタイプです。人の1型糖尿病に類似し、犬ではこのタイプが多いと言われています。
もう1つは、産生・分泌されたインスリンの機能が障害されたり、インスリン分泌量が減少するタイプです。人の2型糖尿病に類似し、猫に多いタイプです。
治療は、どちらのタイプも1日2回のインスリンの注射と基礎疾患があればそちらの治療が基本となります。また近年ではインスリンの注射以外に、1日1回の経口薬も開発されました。全ケースではありませんが、後者のタイプの一部において使用でき、治療の幅が増えてきています。
糖尿病を放置してしまうと、重度の脱水やケトン体という物質が体内に蓄積し、昏睡状態に陥ってしまうこともあります。
また、合併症として、白内障やぶどう膜炎、膀胱炎、皮膚炎、腎不全などが挙げられます。
聞き慣れた疾患ではあるものの、決して侮れず、しっかりと対応していくことが重要です。