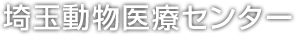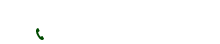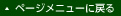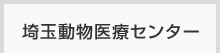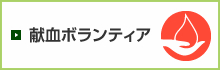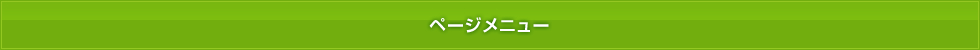眼の病気
角膜潰瘍
角膜潰瘍について
角膜(いわゆる黒眼)に傷がついた状態を角膜潰瘍と言います。はじめは小さな傷でも、悪化すると穴が空いてしまう(角膜穿孔)こともあります。角膜潰瘍を深さにより、表層性、深層性(実質性)、デスメ膜瘤、角膜穿孔に分類することができます。また、角膜潰瘍を臨床的に大きく分けて、治療しなくても7日以内に治癒する表層性の単純性潰瘍と、すでに潰瘍が実質性以上に深い、もしくは表層性でも7日以上治癒しない非単純性潰瘍に分類されます。
症状
眼脂が出る、眼をしょぼしょぼさせる、充血しているなど。
診断
フルオレセイン染色を用いて、角膜表面に潰瘍になっている場所は、ブルーライト下で緑色に染まります。
原因
角膜潰瘍の発症要因は、角膜上皮の喪失が過度になる場合と、その保護・再生力が低下する場合に分類されます。特に非単純性潰瘍の場合、角膜の保護治療のみならず、原因の追究と除去や治療も大事になってきます。
よく見られる角膜潰瘍を引き起こす原因としては、眼瞼内反や睫毛異常など内因性のもの、シャンプーやドライヤーの熱、物理的要因などがあります。また、ステロイドなどの薬剤や点眼液中の防腐剤も角膜上皮に障害を引き起こすことがあります。ドライアイ、短頭種に認められる兎眼、顔面神経麻痺などの眼の疾病でも合併症として角膜潰瘍を招くことがあります。クッシング症候 群、糖尿病などの全身性疾患も、角膜上皮の保護力・再生力低下を引き起こす要因となります。
治療
単純性潰瘍
角膜の保護治療および予防的抗菌薬治療を実施します。
非単純性潰瘍
角膜の保護治療に、考えられる原因に対する治療、感染症を併発している場合は積極的な抗菌薬治療を実施します。内科的治療では進行を抑制しきれない場合、治療用コンタクトレンズによる保護、もしくは外科的治療を選択します。
チェリーアイ(瞬膜腺脱出)
チェリーアイ(瞬膜腺脱出)について
瞬膜腺とは瞬膜の裏にある涙液を分泌する腺で、涙液層の35%を提供しています。涙液腺が本来あるべき位置から離脱してしまった状態を瞬膜腺脱出(チェリーアイ)と言います。多くは瞬膜の上方に突出し、さらに慢性の露出により腫脹します。
原因がはっきりと分かっていませんが、瞬膜腺と周囲組織の結合性が弱くなったことが考えられています。多くは両眼あるいは片眼のみに見られ、2歳齢までに発症します。アメリカン・コッカー・スパニエル、ラサ・アプソ、ペキニーズなどによく遭遇し、猫での発生は犬よりも稀ですが、バーミーズ、ペルシャ、ドメスティック・ショートヘアなどでの報告があります。
瞬膜腺が涙液を分泌しているため、チェリーアイを放置するとドライアイの発症率が高くなることが知られており、それゆえにチェリーアイは手術による制服が必要になります。
かつてのチェリーアイに対する外科手術は、脱出した瞬膜腺の全切除でしたが、現在、涙液分泌の観点から、瞬膜腺を温存する手術が推奨されています。瞬膜腺を温存する手術は、瞬膜腺をどこかに固定する手術法(アンカー法)、作製したポケットに収納する術式(ポケット法)とに大別されます。
白内障
白内障について
白内障とは、本来透明であるはずの水晶体や水晶体嚢が様々な原因で変性し、不透明になった状態を指します。その原因として、加齢、外傷、遺伝、放射線、先天性、糖尿病、ナフタレン中毒など様々なものがあります。
白内障は一般的に、高齢動物に発症すると理解されていますが、実際は若齢でも発生の多い病気です。また、若齢で発生した場合、進行が速く、目の炎症や緑内障、網膜剥離などの合併症を引き起こし、完全に失明してしまうことも少なくありません。。
白内障の進行度合いにより、下記の4ステージに分けられます。
| 初発白内障 | 初期に見られる小さく、限局的な混濁です。水晶体の15%程度までの混濁を指します |
|---|---|
| 未熟白内障 | 混濁が広がっているが、視覚が確保されていると判断される状態。 |
| 成熟白内障 | 全域に水晶体の混濁が見られ、視覚を失った状態。 |
| 過熟白内障 | 水晶体の内容物が溶け出して、水晶体の体積が減少した状態。 |
白内障の発生時期により先天性、若年性、成年性および老年性に分類されます。
治療
現在のところ、白内障に陥った水晶体を透明にして、網膜に光を到達させることができるの は、手術が唯一無二の方法です。しかし、白内障の確実な内科療法がないからといって、白内障を放置すると、様々な合併症が起こります。特に白内障化した水晶体から内容物が溶け出すと、眼内に炎症を起こし、水晶体起因性ぶどう膜炎(LIU)を生じます。
ある報告によると、白内障を放置した全ての症例が0.9年(中央値)で緑内障や水晶体脱臼など、動物にとって苦痛を伴う合併症を発症すると報告しています。また、この報告では、抗炎症薬の 点眼を実施した症例では6割弱が1.5年(中央値)で苦痛を伴う合併症により失明している一方、外科手術を実施した症例では2割が2.9年(中央値)で苦痛を伴う合併症により失明していると報告しています。このことから手術が最も良い治療方法と言えますが、内科療法でも合併症の発症するリスクを低減するのに有用であると分かります。
したがって、白内障の内科療法は水晶体起因性ぶどう膜炎の治療が主な治療となります。眼内炎症が軽度であれば非ステロイド系消炎鎮痛薬、重度であればステロイドの点眼を使用します。
核硬化症
核硬化症について
目が白くなってきったとの主訴で来院された症例の中で、白内障以外に核硬化症と診断される症例もいます。核硬化症は高齢動物でしばしば認められます。
核というのは水晶体の核のことで水晶体の中心部分にあります。水晶体の細胞が成長し脱核して水晶体繊維となります。水晶体繊維は一生涯成長を繰り返すため、成長と共に水晶体繊維数が増加し中心部分(核)の水晶体繊維が圧縮され密度が高くなり、固くなります。圧縮された中心部分は、光の拡散により青みがかった白色に見え、これが核硬化症と言います。
核硬化症では水晶体の繊維が変性し白濁しているわけではないため、視覚を障害することはなく、治療対象にはなりません。
遺伝性網膜変性症(PRA)
遺伝性網膜変性症(PRA)について
犬の遺伝性網膜変性症は網膜の変性が起こり、進行性に見えにくくなり、最終的に失明する遺伝性の網膜疾患です。進行性網膜萎縮症、遺伝性網膜症など様々な名前があります。
網膜の変性は視細胞の桿体または錐体のどちらか一方、あるいはその両方の異常から始まり、最終的に網膜全層に変性が及び、失明に至ります。
症状
臨床現場で多く認められる遺伝性網膜変性症は、桿体細胞から始まる異常が多いため、夜盲が初期症状として現れることが多く、やがて動体視力が低下し目立つようになります。夜盲は数ヶ月~数年にかけて昼盲、全盲へと進行し、最終的に失明します。
また、症状が進むと対光反射が鈍くなり、散瞳気味となります。そこにタペタム領域の反射亢進が加わると眼の輝きが増し光ように見えます。
網膜変性症の進行に続発して白内障が発症し、そこで初めて目の異常に気づく症例も少なくありません。
診断
通常は純血犬種に見られますが、近年では純血犬種同士の交配種にも見られます。主に眼底の検査所見で両眼にほぼ対称に病変を認めます。タペタム領域において、視神経乳頭を中心とした扇状の反射亢進が見られるが、検査する角度によっては反射が低下したようにも観察されます。同時に網膜血管は減少し、狭細化します。症状が進行すると、視神経乳頭は萎縮により白色~灰色化、乳頭陥凹が認められ、ノンタペタム領域に、色素集塊増加や脱色素病変が認められます。
白内障などで眼底検査を実施できない症例に関しては網膜電図検査を実施する場合もあります。網膜電図検査は桿体細胞と錐体細胞の機能異常を初期の段階から個々に調べられます。
治療
現在、遺伝性網膜変性症の進行を抑制または停止させる実用的な治療方法はありません。実際には抗酸化症を有する様々なサプリメントを処方することが多いです。。
網膜剥離
網膜剥離について
網膜剥離とは、網膜が下部組織である脈絡膜から分離した状態を指すが、実際には網膜色素上皮細胞と視細胞の間で分離しています。網膜が剥離すると脈絡膜からの血行が滞り、視細胞の障害や減少が起こり、結果として視覚が低下もしくは消失します。
原因
裂孔性
網膜に裂孔が生じ、液体化した硝子体が網膜下に侵入し剥離が進行します。犬で最もよく認められる原因です。
滲出性
網膜の下に液体が貯留して起こります。原因として全身性疾患を含む感染症、炎症性疾患、血液疾患、血管疾患などが挙げられます。猫では高血圧による網膜剥離や感染症による網膜剥離がよく認められます。
牽引性
後部ぶどう膜炎による硝子体内での膜状物の形成や、水晶体前方脱臼による硝子体の前方移動などにより、網膜が牽引されることによって起こります。
診断
眼底検査により行われるが、時にはペンライトまたはスリットランプでも水晶体後方に存在する剥離した網膜を見つけることができます。
眼底検査にて、部分的に剥離した部位はタペタム反射低下として認められます。網膜剥離が重度になると周辺部位と視神経周囲のみで接着し、その他の部分が剥離してアサガオの花のように網膜が前方に張り出している状態で認められます。場合によっては周辺部分で網膜が大きく裂開し、背側網膜が腹側に下垂した状態で認められることがあります。
また、出血などにより眼内の混濁で眼底検査ができない場合は超音波検査で剥離した網膜を描出することができます。
治療
治療は原因より異なりますが、可能な限り早く剥離した網膜を復位することです。
裂孔性の場合は、剥離した網膜を復位し、再剥離を防止するためにレーザーで凝固し癒着させる必要があります。剥離が部分的な場合や裂孔のみが認められる場合は、進行を抑える手技として散瞳した瞳孔から半導体レーザーを照射し、裂孔周囲もしくは剥離した網膜周囲を凝固する方法があります。
滲出性の場合は、原因となる基礎疾患もしくは炎症に対して内科的治療を行い、液体を吸収させます。
牽引性の場合は、牽引の原因となっている硝子体の膜状物の切除が必要になります。
予後
早期に剥離した網膜が復位できれば視覚の回復が可能ですが、網膜の変性が起こることが多いです。網膜が復位できても、剥離している期間が長ければ視細胞の減少が起こり失明は永久的となります。剥離期間は短ければ短いほどいいですが、1週間以上経過した症例では視覚の回復は困難とされています。また、視覚喪失だけでなく、目の炎症や続発緑内障を引き起こすなど将来にわたって経過観察が必要となります。