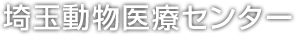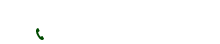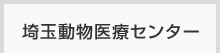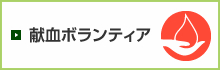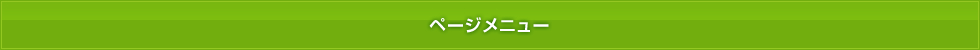神経・筋肉の病気
水頭症
水頭症とは?
側脳室内に脳脊髄液が病的に蓄積した状態を水頭症といい、様々な小型犬種、幾つかの大型犬種、猫などで先天的に発症することが知られています。先天性水頭症の多くは中脳水道という細い脳脊髄液の通り道が狭窄することで脳脊髄液の流れが滞り、左右両側の側脳室が障害を受けますが、脳内の全ての脳室(側脳室、第三脳室、第四脳室)が拡張することもあります。
水頭症は後天性に起こることもあり、① 脳腫瘍などによって脳脊髄液の流れが阻害される、② 脳組織の一部が脳梗塞や外傷などによって壊死を起こし、脳が無くなった空間を脳脊髄液が埋める、などの原因によって起こります。これらは多くの場合MRIの画像で区別でき、②の水頭症は治療の必要がありません。
なお、臨床的には正常な小型犬種でも、水頭症を思わせる脳室拡大が認められることも多いですが、明確な治療基準は存在しません。
症状
水頭症の患者は様々な神経症状をあらわします。意識状態が低下して活気がない状態や、トイレトレーニングやしつけなどの学習能力が低いことがよくあります。症状が進むと失明、歩行障害がみられ、重症例ではてんかん発作や昏睡状態を起こすこともあります。
最近の小規模研究では、意識レベルの低下や元気消失は100%認められたのに対して、てんかん発作は17%程度の犬にしか認められていませんでした。
診断
特に小型犬では臨床的には正常でも水頭症を思わせる脳室拡大が認められることも多いため、MRI上での脳室拡大だけで水頭症の診断は下せません。診断には患者の年齢、病歴や神経学的検査がとても大切です。また、場合によっては超音波検査を用いて脳圧亢進の有無を調べることもありますが、主観性の高い検査なため経験の多い獣医師が行うことが勧められます。
治療
通常は内科療法により脳圧を下げる治療や脳脊髄液の産生を抑える治療を行いますが、内科療法に反応しない症例では脳室内の脳脊髄液を腹腔内に流す管を設置する手術(VPシャント)を行います。VPシャントは感染の危険性が高いことから、クリーンルームの手術室を備えた施設で十分な準備を行って行うことが必要です。術後の短期的な経過は比較的良好ですが、長期的にはシャントに感染や詰まりなどの問題が多く起こること報告されています。
予後
水頭症は古くから知られてきた病気ですが、ごく最近まで外科手術の成績を評価した研究はありませんでした。上述した通り術後の短期的な経過は一般的に良好ですが、長期的にはシャントに問題が発生することが少なくなく、25-70%の確率で問題が生じたと報告されています。
内科療法の成績は重症度によります。症状が重度な患者は内科療法で改善する可能性が低く、脳が本当に薄い症例では外科手術の危険性も高まるため手術が勧められない場合もあります。