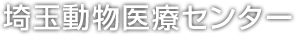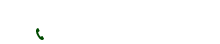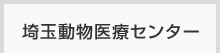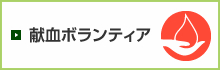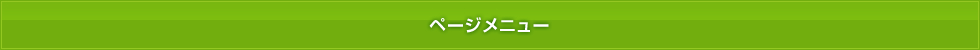脳炎・髄膜炎について
犬や猫は他の動物と同様に、様々な病原体の感染によって脳炎や髄膜炎にかかります。
代表的なものとして、狂犬病、犬ジステンパーウイルス、猫伝染性腹膜炎ウイルスなどのウイルス感染、外傷や内耳炎などによる細菌感染、エーリキアなどのリケッチア感染、ネオスポラやトキソプラズマなどの原虫感染、クリプトコッカスなどの真菌感染などが挙げられます。
しかし、特に犬では病原体が見つからないタイプの脳炎が最も多く、詳細な原因は解明されていないものの、免疫介在性の疾患(免疫システムが異常を来たし、自分の身体の一部を攻撃してしまうもので、アレルギー反応と類似)であることが疑われています。この免疫介在性が疑われる髄膜脳炎には、肉芽腫性髄膜脳脊髄炎(GME)、壊死性脳炎(NME、NLE)、ステロイド反応性髄膜炎動脈炎(SRMA)などが含まれていますが、特に前者2つの確定診断には脳組織の病理検査が必要となります。
GME
中年齢(4-8歳)の小型犬、特にテリア系の避妊雌に多く認められることが広く知られていますが、大型犬を含めて様々な犬種や年齢の患者が罹患することが報告されています。
ウイルス性脳炎に類似した病変分布を起こすため、Schazbergらのグループによって様々な病原体を検出する試みがされてきましたが、一貫した病原体は見つかっていません。
壊死性脳炎
パグ、ヨークシャーテリア、フレンチブルドッグ、チワワなどで報告があり、名前の通り脳組織の一部が壊死を起こすことが特徴の一つです。比較的若い犬に多く認められますが、10歳齢の報告もあり、GMEと同様に幅広い年齢層で罹患する可能性があります。
SRMA
髄膜上の細い動脈が炎症を起こす疾患で、ビーグルペインシンドロームとも歴史的には呼ばれていました。
5-18ヶ月齢の若い犬が重度の頸部痛を起こすことが特徴的で、発熱を伴うこともあります。ボクサー、ビーグル、バーニーズマウンテンドッグ、ジャックラッセルテリアなどに多く認められ、通常、急性期には重度の頸部痛が一般的に認められます。慢性的になると髄膜の肥厚や脳脊髄障害などが認められることがありますので、発症時に正確な診断を行い積極的な治療を行うことがとても重要です。また、治療には長期間を要するため、途中で治療を停止すると再発が多く注意が必要です。
症状
脳や脊髄の中でどの部分がどの程度炎症を起こすかによって様々な症状が認められます。てんかん発作、頸部痛、歩様異常、身体の麻痺などの明らかな神経の症状を起こすことが多いですが、一方で何となく元気がない、どこかを痛がる、食欲がない、などの原因を特定することがとても難しい場合も少なくありません。
診断
診断にはMRIと脳脊髄液検査の両方が必要となります。両検査ともに全身麻酔が必要となるため、通常は麻酔をかけた際に両方の検査を同時に行います。
また、感染性脳炎でないことを確認するために、ウイルスなどの病原体を検出する検査を追加することもありますが、地域によってそれぞれの感染症の危険性が異なるため、お住まいの地域によって検査する項目が異なります。
壊死性脳炎は一般的に治療に対する反応が思わしくないため、様々な研究者や獣医神経科医、病理医などが生前診断を模索していますが、現段階では脳組織の一部を採取せずに壊死性脳炎やGMEを確定診断する方法はありません。しかしながら、脳組織の生検には特殊な機器が必要となり危険を伴いますので、多くの場合は犬種、年齢、臨床経過、MRI検査の結果や脳脊髄液検査の結果などを総合的に判断して暫定的な診断を下します。
治療
免疫介在性疾患であることが疑われる場合には、ステロイド剤や免疫抑制剤を併用することが一般的です。様々な免疫抑制剤の治療効果が報告されていますが、どれも規模が小さく、確定診断が行われていないものや、治療後の経過が悪くて亡くなってしまった症例に使用した治療方法を比較検討するという手法がとられていることもあり、数多くある研究を比較検討する上で大きなジレンマとなっています。そのような状況ですので、獣医神経科医によって最初に使われる免疫抑制剤は数種類に分かれます。
予後
髄膜脳炎の予後を予測することは一般的に難しい場合が多く、治療に対する初期反応によって判断されます。
壊死性脳炎が疑われる患者の予後は特に注意が必要ですが、GMEなども一部の患者では急激に症状が悪化したり、積極的な治療をしても数日以内に亡くなってしまうことがあるため予後には十分な注意が必要です。
ステロイド剤や免疫抑制剤にはそれぞれ固有の副作用がありますので、診断および治療は経験の多い神経科医のアドバイスを受けることが勧められます。